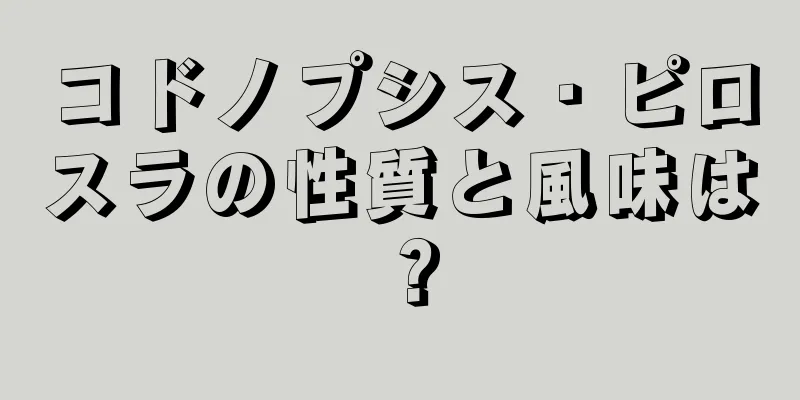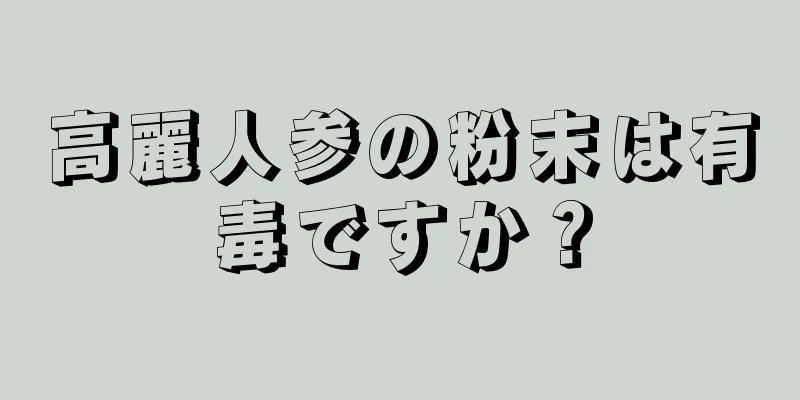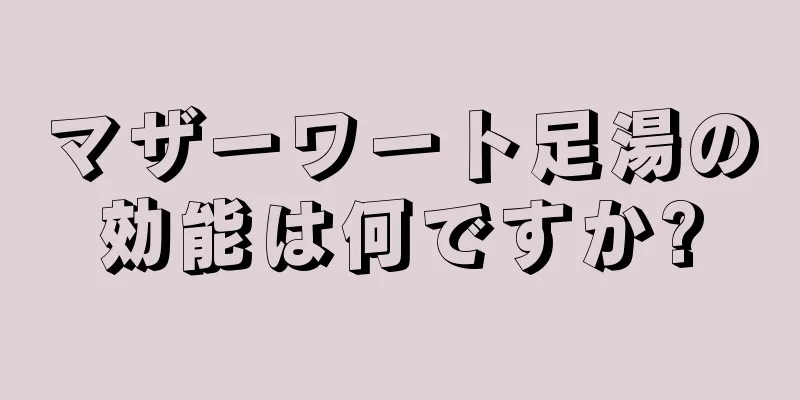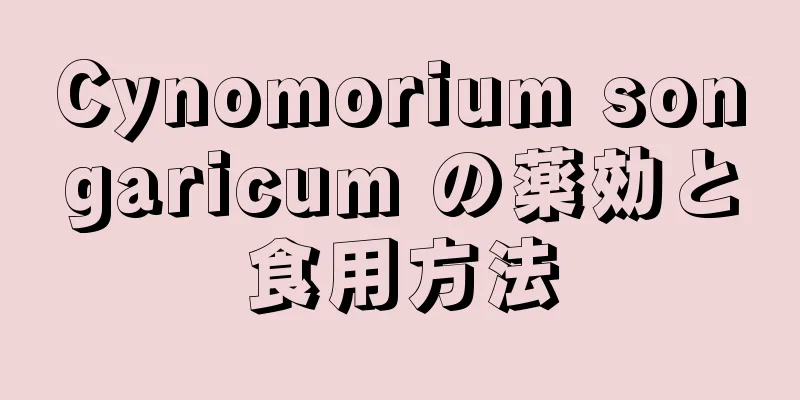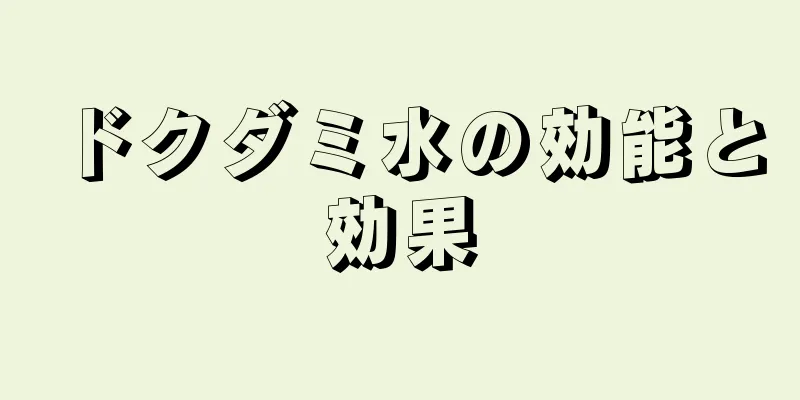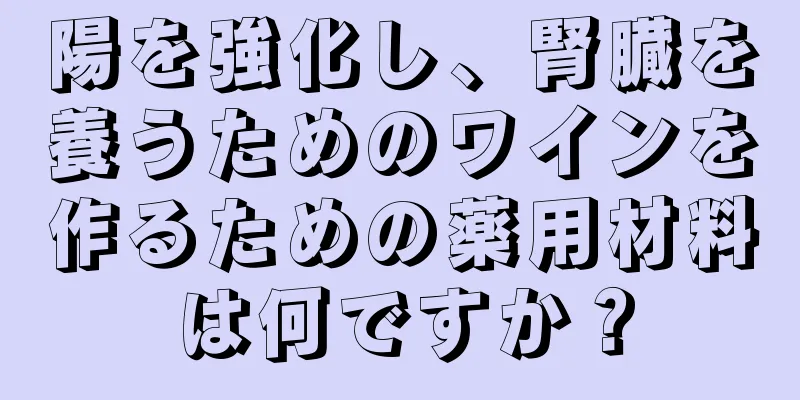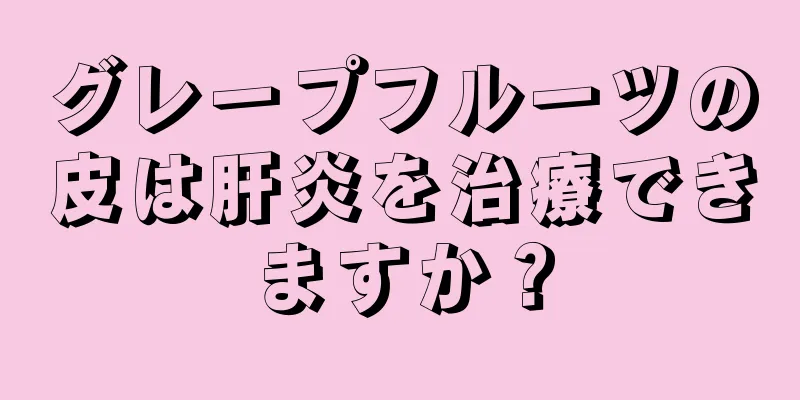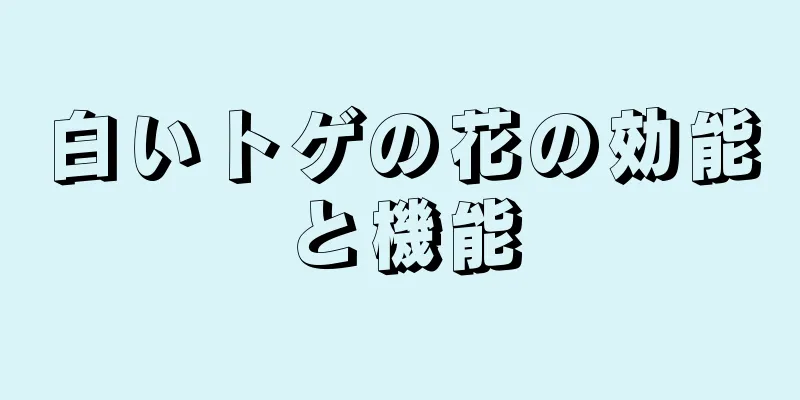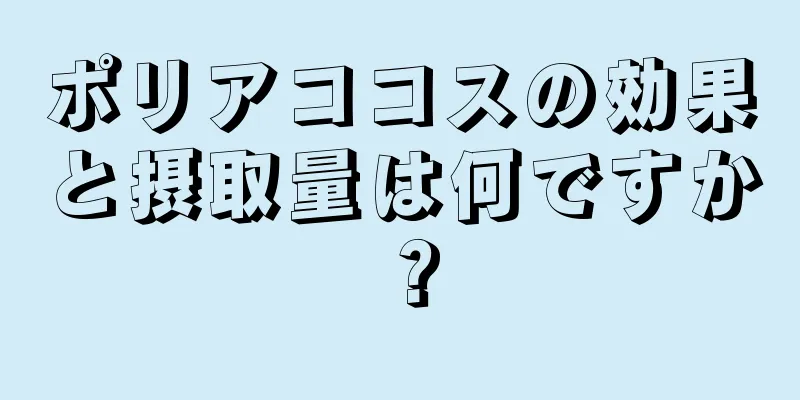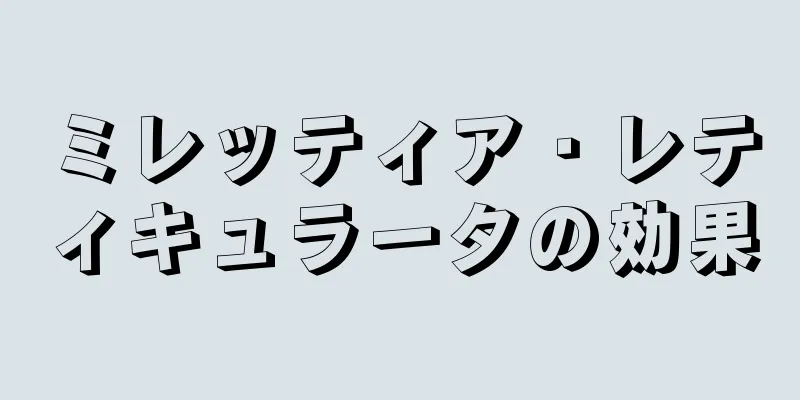クローブの効果とは
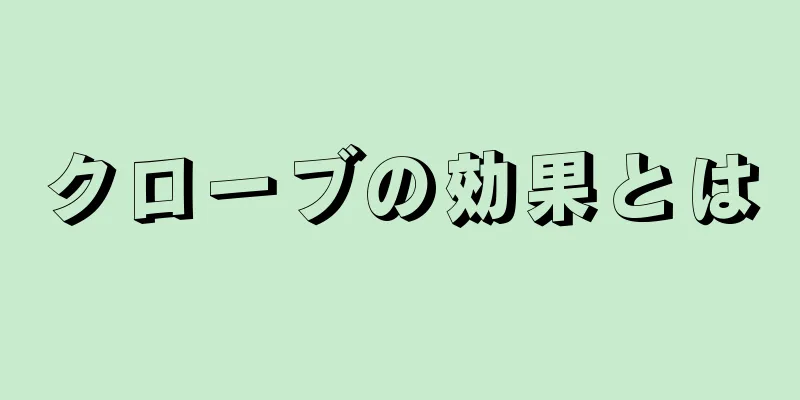
|
雄クローブはフトモモ科の常緑樹の花芽を指し、ギンバイカの果実は雌クローブと呼ばれます。クローブは、伝統的な中国医学では特定の薬効を持つ植物でもあります。胃や腎臓の病気、インポテンツの治療に効果があります。西洋医学では難しく複雑な病気の多くは、伝統的な中国医学ではゆっくりと治療する必要があります。クローブは、いくつかの頑固な病気の治療に非常に効果的です。それで、クローブの効果は何でしょうか? クローブはフトモモ科の植物の花芽です。ライラックも常緑樹で、原産地はマレーシア諸島とアフリカです。もちろん、我が国でも広東省、海南省、広西チワン族自治区、雲南省などでも少量栽培されています。クローブには多くの機能と効果があるため、伝統的な漢方薬で使用すると、頑固な病気の治療に非常に役立ちます。 クローブの芽はわずかに乳棒のような形をしており、わずかにT字型で、長さは1〜2cmです。花は球形で、直径0.3~0.5cm、花弁は4枚、重なり合って抱き合い、茶色または黄褐色で、花弁には多数の雄しべがあり、花糸は湾曲し、花柱は直立し、萼筒は円筒形でわずかに平らでわずかに湾曲し、長さ0.7~1.4cm、直径0.3~0.6cm、赤褐色または茶色で、上部に十字形に分かれた4枚の三角形の萼片があります。食感は硬く油分が豊富で、水に入れると萼筒が垂直に沈みます。香り高く、舌が痺れるような辛味があります。最高のものは油分が豊富で香りが強く、水に沈みます。 丁子は辛味と温味があり、脾臓、胃、腎の経絡に入り、芳香と消散作用があり、中を温めて悪影響を取り除き、寒を分散させて痛みを和らげ、腎を温めて陽を補う作用があります。主に胃寒としゃっくり、嘔吐と吐き気、下痢と赤痢、腎虚とインポテンツ、陰の冷えヘルニア、腰と膝の冷え、陰の癰、口臭、壊血病の治療に使用されます。 以上がクローブの効果の紹介です。クローブの薬効は非常に高いことがわかります。ただし、薬物治療のためにクローブを摂取する場合は、必ず医師に相談してください。そうしないと、身体に不快感を引き起こし、病気を悪化させます。さらに、クローブは治療薬としても使われます。肉にクローブを加えて煮込むと、体を整えながら味覚を満足させることができます。 |
推薦する
揚げたポリアココの効果と機能は何ですか?
キノコは菌類の食べ物であり、多くの種類があることは誰もが知っています。よく使われる漢方薬の原料である...
キジの効能と機能
ご存知のとおり、キジは長年の歴史を持つ非常に一般的な薬用素材であり、多くの病気を治療することができま...
ロディオラ・ロゼアの効果、機能、摂取方法は何ですか?
ロディオラ ロゼアは貴重な漢方薬として、人体の多くの病気に対して優れた予防効果と治療効果を発揮するこ...
霊芝酒のレシピは何ですか?
現代社会では、誰もが自分の体の健康に非常に気を配っています。自宅で薬酒を作ることは、体の健康に非常に...
Di Gu Piの副作用は何ですか?
地固皮は寧夏クコの根皮で、清熱、肺火消、清血の効能があり、優れた滋養強壮薬であることは周知の事実です...
美しいLespedeza根の効能と機能
現代医学の研究では、美濃焼の根には人体に有益な栄養素が多く含まれていると考えられています。伝統的な漢...
臭い梅の効能と効果
臭梅は薬用物質です。その薬効をある程度理解していれば、臭梅を正しく使用して生活における関連する病気を...
オタネニンジンでそばかすを消す方法
三七人参は伝統的な中国の薬材です。三七人参の粉末には、そばかすを除去し、美白する効果があります。三七...
霊芝の薬効
薬は生活の中でとても一般的です。薬によって病気の治療効果は大きく異なります。そのため、薬を選ぶ際には...
石ナツメの効能と機能
伝統的な中国医学の石ナツメの効能と機能は非常に優れています。私たちは生活の中で石ナツメをよく見ること...
ヒメツルカズラの効能と機能
ヤナギランは伝統的な中国の薬材です。このタイプの薬は病気の治療の多くの側面をカバーすることができるの...
空樽人参の効能と機能
高麗人参は非常に一般的な漢方薬であり、また非常に重要な薬材でもあります。私たちはそれに注意を払う必要...
ヨモギの効能と機能
ヨモギは、体の栄養成分を補うだけでなく、体のさまざまな機能を調整するのにも役立ちます。また、高い薬効...
莙子の効能と機能
漢方薬は特定の病気の治療に予期せぬ効果をもたらすことが多いため、安心して選ぶことができます。しかし、...
麻魚骨の効能と機能
伝統的な漢方薬は、いくつかの特殊な病気の治療に非常に効果的ですが、服用する前にそれについて学ぶ必要が...