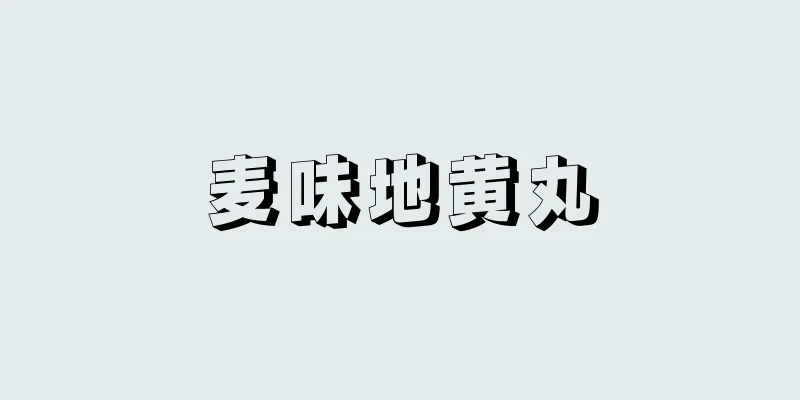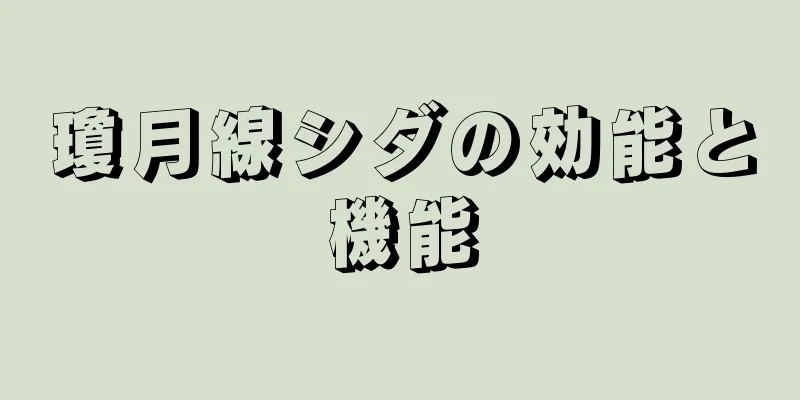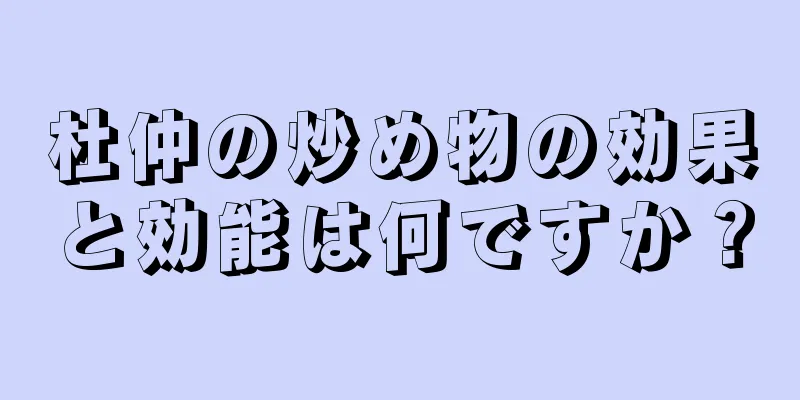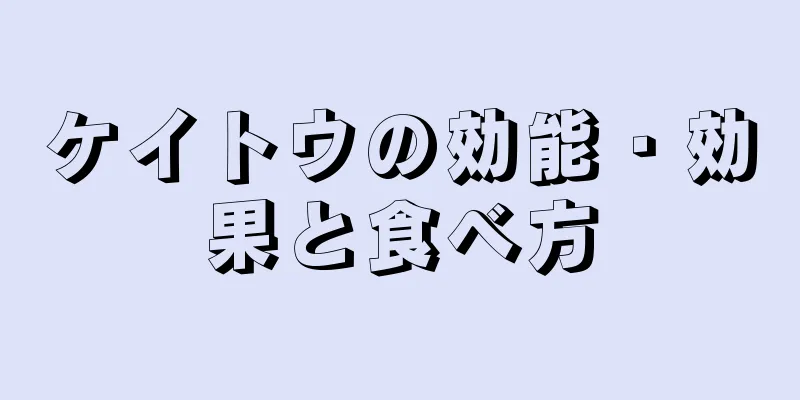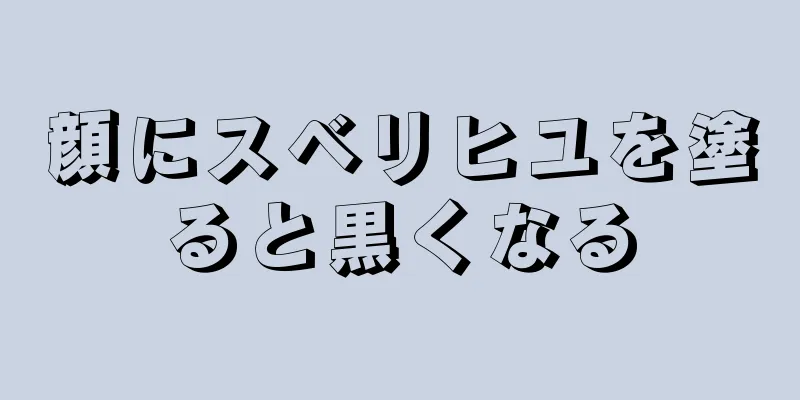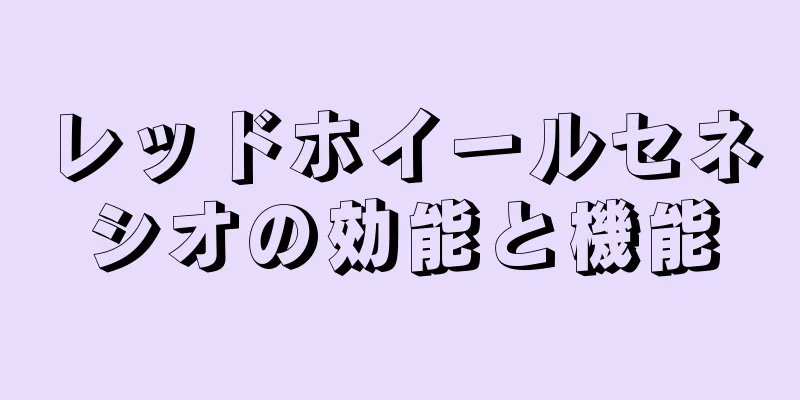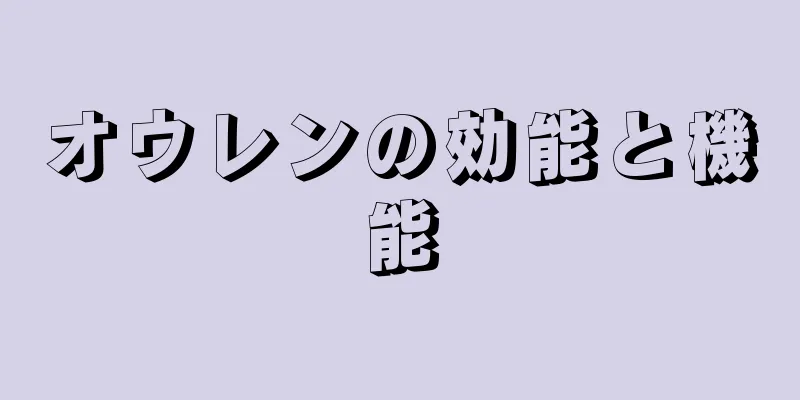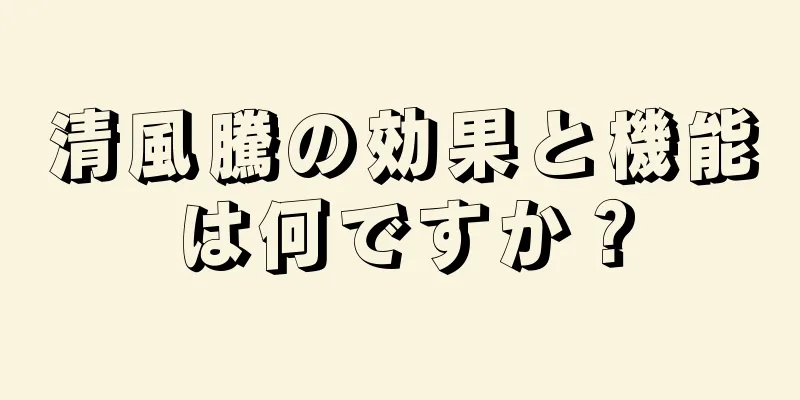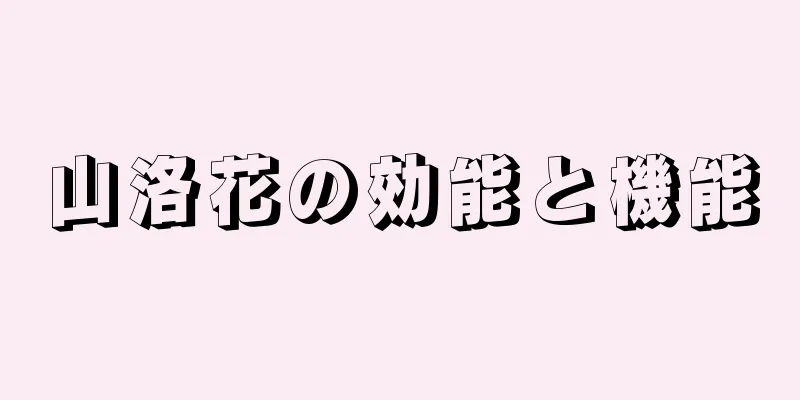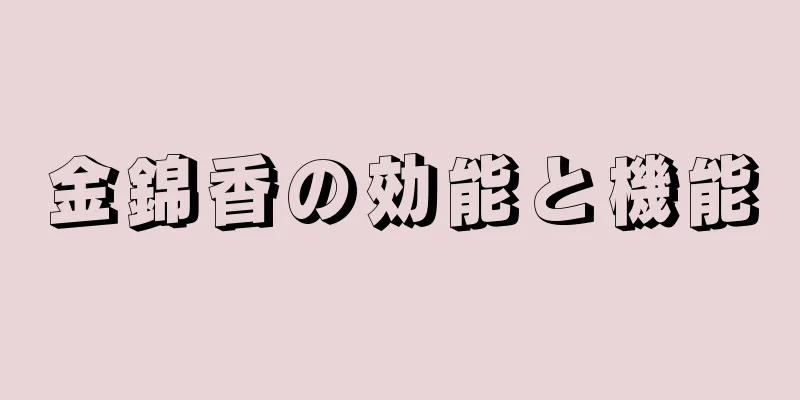四十散と半夏茯苓湯の効果は何ですか?
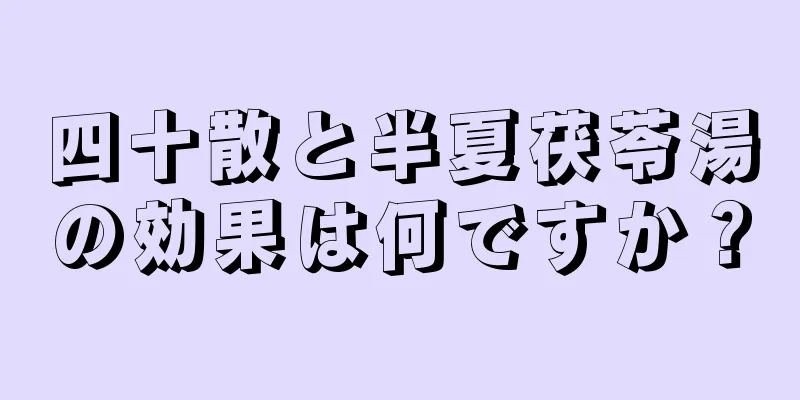
|
昔、病気になると、人々は必ず漢方薬を飲んでいました。医者から薬の材料をもらって、自分で煎じ薬を作っていたのです。面倒なだけでなく複雑でもありますが、社会の継続的な進歩に伴い、現在では中国の特許医薬品もいくつか市場に出回っています。誰にとっても服用がはるかに便利になるだけでなく、効能も同じです。その中でも、四十散と半夏茯苓湯の効能についてご紹介します。 半夏希心煎じ薬 【名称】半夏茯苓煎じ薬 [分類] 和合剤 - 寒熱を調整する 【構成】 洗ったオウゴン 1/2 リットル (12g)、オウゴン、乾燥ショウガ、高麗人参 3 両 (各 9g)、黄連 1 両 (3g)、ナツメ 12 片 (4 片)、ローストした甘草 3 両 (9g) 【用法】上記7つの成分をとり、水1斗を加えて沸騰させて6リットルを取り出し、残渣を取り除いて再度沸騰させ、3リットルを取り出し、温かいうちに1リットルを1日3回服用します。 【効能】冷えと熱のバランスを整え、腫れを解消し、腹部の膨満感を和らげます。 【レシピ説明】 この処方で治療する腹部膨満は、小柴胡煎じ薬の誤った使用によって引き起こされ、中陽を損傷し、外邪が体内に入り、寒熱の組み合わせを引き起こし、心臓の下に腹部膨満を形成します。 「ぴ」は閉塞や障害があり、上部と下部が互いに連絡できないことを意味します。心臓の下の領域は胃の空洞であり、脾臓や胃の病気と関連しています。脾臓と胃は中焦に位置し、陰陽の盛衰の中心です。中気が弱ると寒熱が絡み合い、腹部にしこりが生じます。中枢の気気が損なわれると、気の盛衰が異常となり、嘔吐や腸鳴り、下痢などの症状が現れます。治療は寒熱を調整し、気を強め、胃を調和させ、しこりを分散させ、腹部の膨張を解消することです。この処方は、辛味と温感を持つ芍薬を主成分としており、腫れを分散させ、腹部の膨満感を解消するほか、吐き気や嘔吐の緩和にも効果があります。私は、乾燥ショウガの辛味と熱味を利用して、体を温めて冷えを解消し、オウゴンとオウレンの苦味と冷味を利用して、熱を取り除き、腹部の膨張を和らげます。上記の4つの薬を併用することで、寒熱のバランスを整え、辛味で体を開き、苦味で体を弱める作用があります。しかし、寒熱併発は、中臓の虚弱と昇降障害によるものです。そのため、この処方では、人参とナツメの甘温作用で脾臓を養い、脾臓の虚弱を補います。さらに、松涛を配合して昇降作用を持たせ、脾臓と胃の昇降を正常に戻します。甘草は脾臓を養い、中枢を調和させ、他の薬の作用を調整するために使用されます。処方全体は、寒と熱で陰陽を調和させ、苦と辛でその盛衰を調整し、補気と下気で虚と過剰を補うのが処方の特徴です。冷えや熱を和らげ、血液循環の正常な上昇と下降を回復し、膨満感、嘔吐、下痢が自然に治ります。 この処方は柴胡と生姜を除いた小柴胡煎じ薬で、黄連と乾燥生姜を加えたもので、少陽和合剤となり、冷えと熱を整える処方となる。後世の人たちも彼の方法を踏襲し、症状に応じて薬を加減し、寒熱混合や昇降不均衡などのさまざまな症状に広く応用しました。 【処方歌】 芒草、芍薬、黄連、黄耆、生姜、甘草、高麗人参、ナツメを合わせて虚弱と腹部膨満を治療します。その方法は陽を下げ、陰を調和させるというものです。 シニサン: 韻 四十散には柴胡、芍薬、黄耆、甘草などが使われます。これは陽鬱が冷えや逆昏睡の原因となり、陰鬱を鎮め調和させることで冷えを解消できるからです。 構成 ミシマサイコ、シャクヤク、未熟なビターオレンジ、リコリス。 投与量 甘草(焙煎したもの)、未熟なビターオレンジ(砕いて水に浸し、焙煎して乾燥させたもの)、ミシマサイコ、シャクヤクを各6g。 使用法 上記の4つの材料をすりつぶしてふるいにかけ、1平方インチを白水とともに1日3回摂取します。現代の用法: 水で煎じて飲む。 関数 病原菌を排出し、鬱を和らげ、肝臓を鎮め、脾臓を調節する 適応症 1. 陽鬱と失神。手足が冷えたり、腹痛があったり、便が重く脈が糸を引く下痢があったりする。 2. 肝脾気鬱症候群。肋骨の膨張、上腹部と腹部の痛み、脈の緊張。 ファン・イー この症候群は、主に外邪が経絡を通して内部に侵入し、気の流れを妨げて外に流れ出ないようにすることで引き起こされ、陽気の停滞を引き起こします。治療は主に邪気を排出し、停滞を解消し、肝臓を鎮め、脾臓を調整することを目的としています。陽気が体内で沈み、末端まで届かなくなるため、手足が冷たくなります。このような「四逆」は、陽虚・陰虚によって生じる手足の冷えや逆症状とは根本的に異なります。李仲子はこう言っています。「この症状は四逆症状と呼ばれていますが、必ずしも非常に冷たいわけではありません。指は少し温かいかもしれませんし、脈は深く弱くないかもしれません。それは陰の中に陽が含まれている症状ですが、気が自由に流れていないため、逆寒です。」処方では、柴胡は肝臓と胆嚢の経絡に入り、陽の気を促進し、肝臓を落ち着かせて憂鬱を取り除き、邪気を追い出すため、主な薬です。白芍薬の根は、陰血を養い、肝臓を柔らかくします。柴胡と一緒に使用して、肝血を養い、肝気を調整します。陰血を傷つけずに柴胡を上昇させ、分散させることができます。芝翹は気血を調整し、鬱を和らげ、熱を取り除き、停滞を打破するのを助けます。白芎と組み合わせると、気血を調整し、気血を調和させることができます。甘草は、さまざまな薬を調和させ、脾臓を利し、中枢を調和させるために使用します。 互換性特性 上昇する志士と下降する柴胡の組み合わせは、気を鎮める働きを強化し、清気を上げ、濁気を下げる効果があります。本来のレシピは白湯(米のスープ)で摂取されますが、これもまた、中にある気が調和すると陰陽の気がスムーズに流れるという考えに基づいています。 使用 この処方は楊于覚尼症候群に用いられます。臨床応用においては、手足の冷え、腹痛、または便が重く脈が糸を引く下痢などが症候群鑑別の重要なポイントとなります。 加算と減算 咳がある場合は、五味子と乾燥ショウガを加えて肺を温め、風邪を取り除き、咳を和らげます。動悸がある場合は、桂枝を加えて心臓の陽を温めます。排尿困難がある場合は、排尿を促進するために枸杞子を加えます。腹痛がある場合は、焙煎したトリカブトを加えて内寒を取り除きます。下痢と重い便がある場合は、ニンニクを加えて陽を促進し、停滞を取り除きます。気の停滞がひどい場合は、ミズキとウコンを加えて気を整え、停滞を取り除きます。発熱がある場合は、クチナシを加えて内熱を取り除きます。 中国の特許医薬品である四十散と半夏茯苓湯は、どちらもいくつかの病気の治療に非常に効果的です。しかし、誰もが自分の実際の状況に応じて薬を選択しなければならず、それが身体の病気に大いに役立つでしょう。しかし、どんな病気を治療するにしても、医師の指導の下で治療する方がより安全で効果的だということを誰もが覚えておく必要があります。 |
推薦する
ジオウの効能と機能
地黄は伝統的な漢方薬の一種です。古代中国の医学書には地黄に関する記録があります。地黄は多くの病気を治...
咳と痰に効く漢方薬
咳の症状がある場合、西洋医学による治療を選択することもできますが、もちろん、漢方薬による治療を選択す...
ヘアケアのためのツルドクダミの食べ方
人々はいつも黒くて美しい髪を持つ人を羨ましがっています。しかし、現代の生活では誰もが多大なプレッシャ...
中国産蔬莱ベッドの効能と機能
中国産の賽莢草は伝統的な漢方薬の一種です。人体にとって特定の病気の治療に非常に役立ちます。また、この...
球菌の原因は何ですか?
この病気の原因である球菌は非常に複雑です。多くの人は、この菌が体内に現れても本当の原因を特定できず、...
スイカズラを飲むのに適さない人は誰ですか?
スイカズラは比較的一般的で貴重なハーブです。スイカズラには優れた薬効があり、比較的安価なので、多くの...
三血芎の効能と機能
病気は薬で改善する必要があります。病気によって薬の選択は異なります。病気をうまく治療したいなら、適切...
ミレッティア・レティキュラータの効果と機能は何ですか?
薬用原料のミレッティア レティキュラータは、月経過多や月経困難症など、女性の多くの月経合併症を緩和す...
パパイヤの効能と機能[写真]
漢方薬にはいろいろな種類があります。選ぶときには、まず薬のことを理解する必要があります。それでは、パ...
大飛来草の効能と機能
実際、人間の多くの病気の発生は食事と密接な関係があります。健康な体を手に入れたいなら、食事療法は非常...
キャベツの効能と機能
キャベツとは何かご存知ですか?それは伝統的な中国医学の一種です。古代の医学書にはそれに関する多くの記...
青龍吐水の効能と機能
青龍藤は誰もがよく知っているもので、長い歴史があり、体調を整えて病気を治療する効果があり、健康維持に...
タデ科タデ属の1ポンドあたりの価格はいくらですか?
寿烏は九真藤とも呼ばれ、日常生活でよく使われる漢方薬です。陰と体液を養い、気と血を補い、消化を促進し...
赤よもぎの効能と機能
端午節には多くの風習がありますが、すべて屈原を記念するものです。紅よもぎで顔を洗うのもその一つです。...
三七人参粉末の外用
三七人参粉末は経口摂取だけでなく、外用としても使用できます。三七人参粉末は外用して出血を止めることが...