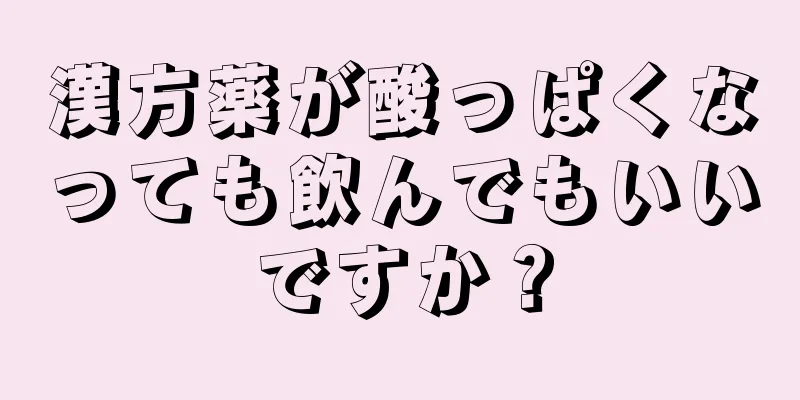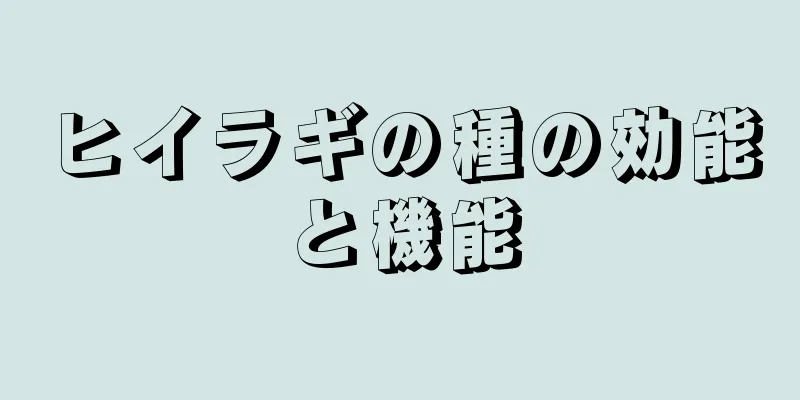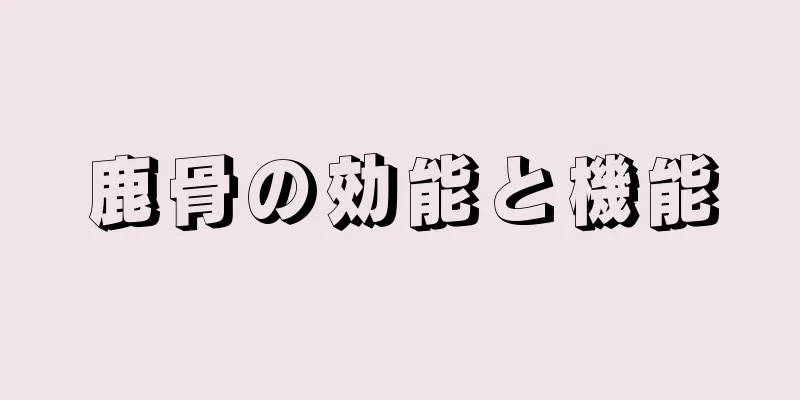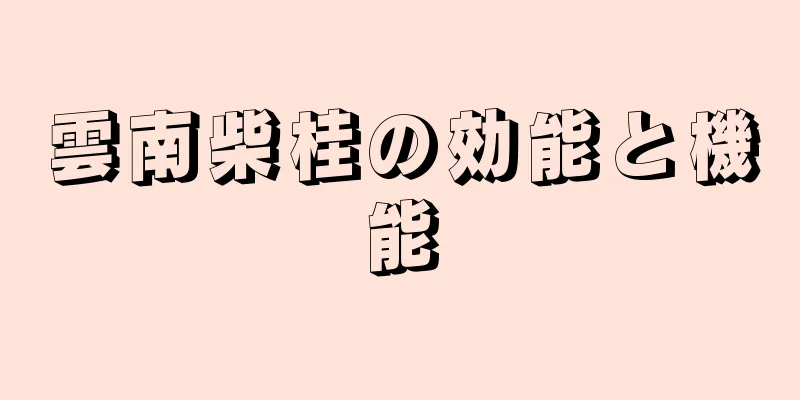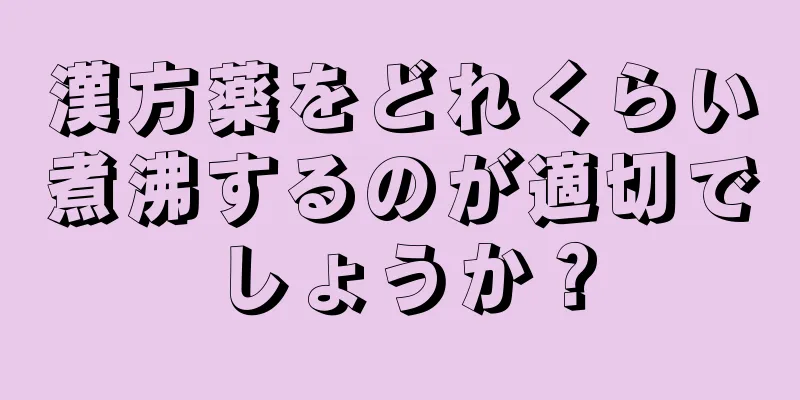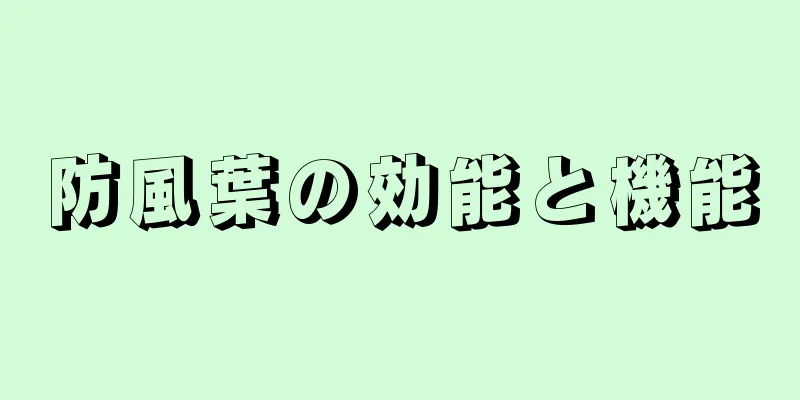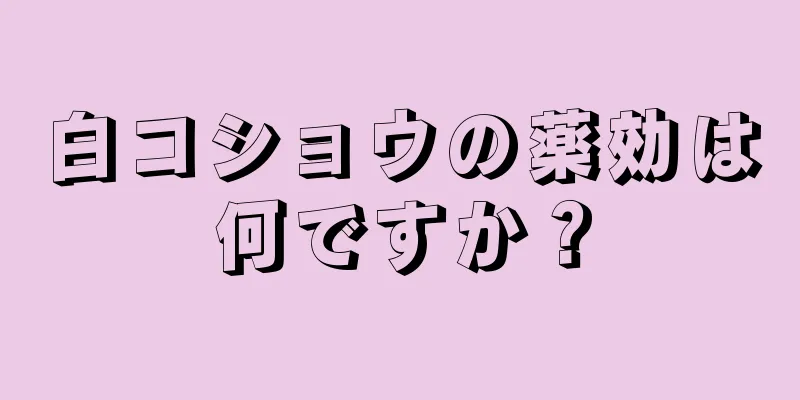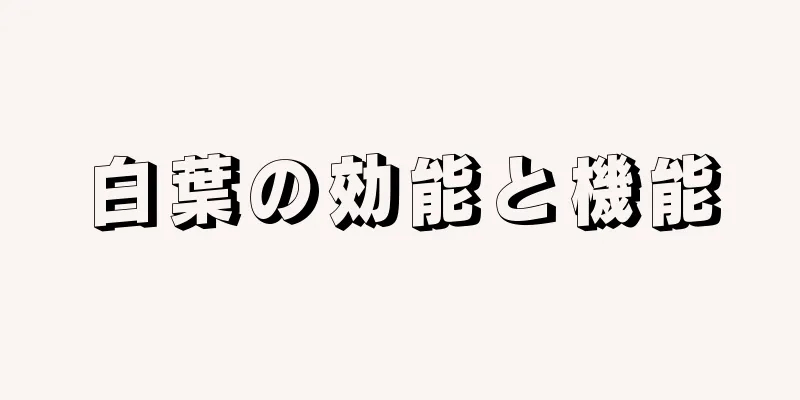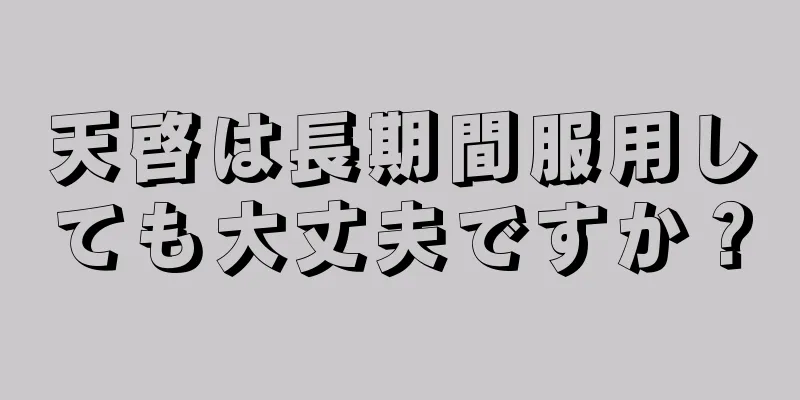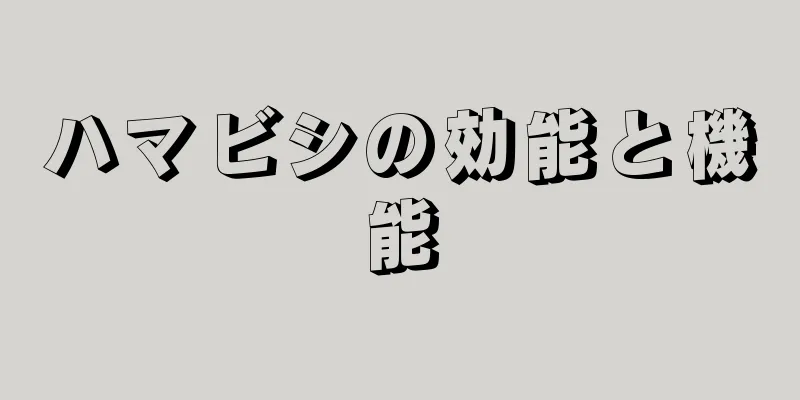黄耆と当帰の効能
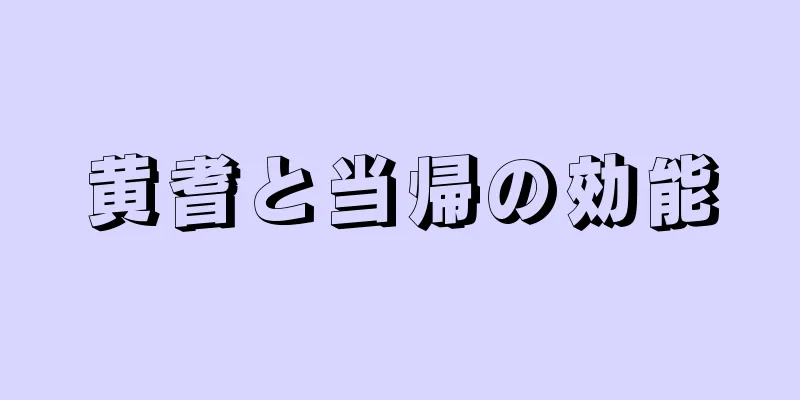
|
黄耆と当帰はどちらも栄養のある食べ物なので、これらを使った食べ物は体に一定の効果があります。どのような種類の食べ物であっても、体に良いものであれば、食べるように努めることができます。そうすることでのみ、体に必要な栄養素を補給できるからです。ただし、前提条件として、これらの食品の効果と独自の栄養価を理解する必要があります。 これから食べる食品の効果や栄養をしっかりと理解し、目的に応じて活用しましょう。ただし、使用プロセス中に注意する必要があるのは、異なるスタイルで提示する場合、互いに互換性のない食品を選択する必要があるということです。では、黄耆と当帰の効果は何でしょうか? アストラガルスの利点 1. 外虚による自発発汗:主に外虚による自発発汗に用いられます。外気がしっかりしておらず発汗がある場合は、黄耆に大根と芍薬を混ぜて服用します。長期間服用すると効果があります。芳乳玉葱豊散。浮麦、麻黄根などと併用することもできます。 2. 陰虚による寝汗:地黄や茯苓などの養陰生薬と併用できます。 3. 急性腎炎による浮腫:陽気不足による無力性浮腫に用いられ、方芎黄耆煎じ薬など方芎、芎芎、青芎などと併用されることが多い。 4. 慢性腎炎、脾腎虚による浮腫:党参、毫托、枸杞子と併用されることが多い。 5. 陽気が弱い:長期間潰瘍化せず、内側に陥没した傷に使用され、潰瘍化を促進し、局所化を制限する可能性があります。癰癬が長期間発症しない場合は、センザンコウ、ムクロジ、当帰、川芎などを併用することが多い。 6. 潰瘍と傷:傷が長期間治らない場合は、組織の再生を促進し、傷を治すことができます。スイカズラ、ムクロジ、オオバコと一緒に使用されることが多いです。膿を排出するためには、党参、桂皮などと併用します。 7. 肺気虚症候群:慢性の咳と喘息、息切れ、疲労感、咳では吐き出せない肺の痰。肺を温め、喘息を緩和し、肺気を強化するために、アスタータタリクス、フキタンポポなどと組み合わせて使用されることが多いです。脾臓は痰を生成し、肺は痰を蓄えるので、痰を排出するためには太陰を強化する必要があります。黄耆は気を補うので、気虚の治療に特に効果的です。 8. 気虚と虚弱:疲労、気の滞り、直腸脱、子宮脱。気力を補い、脾臓を強化する効果があり、党参、枸杞子などと組み合わせて使用されることが多い。また、気力を増強し、陽気を高め、沈んだ気を上げる効果があり、党参、サラシミツ、柴胡、焙煎甘草などと組み合わせて使用されることが多い。 アンジェリカにはアミノ酸も豊富に含まれています。さらに、アンジェリカにはウラシル、アデニン、胆汁アルカロイド、5-ヒドロキシフランアルデヒド、微量元素(亜鉛、銅、鉄、マンガン、カリウム、ナトリウム、カルシウムなど)、リン脂質、ビタミンA、ビタミンB12などの成分も含まれています。 機能及び効能: 効能分類: 強血薬、生理調整薬、鎮痛薬 効果:血液を養う、血液循環を活性化する、月経を調整し痛みを和らげる、腸に潤いと潤滑を与える 効能: 血虚の諸症状、月経不順、無月経、月経困難症、腫瘤の蓄積、不正出血、虚冷による腹痛、麻痺、皮膚のしびれ、腸乾燥・便秘、赤痢後の重苦しさ、癰、潰瘍、転倒外傷。 1) 本品は優れた強血作用があり、血虚による様々な症状に用いられます。 2) 本剤は婦人科領域において月経を調節する重要な薬剤であり、月経不順、無月経、月経困難症等の症状のある女性に用いられます。 3) 血液を滋養し、血行を活発にし、腫れを抑え、痛みを和らげ、排膿し、組織の再生を促進する作用があるため、転倒による外傷、癰、潰瘍などに使用できます。 4) 滋養血、潤腸作用があり、血虚、腸の乾燥、便秘などに効果があります。 用法・用量: 経口摂取の場合: 6~12グラムを水で煎じるか、錠剤や粉末にするか、ワインに浸すか、軟膏として塗布します。 禁忌:体の中央部分が湿気で塞がれ、便がゆるい場合は注意して使用してください。 1.効能・効果:脳卒中による意識消失、口から泡を吹く症状、産後麻痺などの治療に用いられます。 ①抗低酸素作用、②体の免疫機能を調整し、抗がん作用がある、③スキンケア、美容効果、④補血、活血作用、⑤抗菌、抗動脈硬化作用。 黄耆と当帰の効果は、実際に食べることで得られる恩恵です。黄耆は気虚の問題を調整するのに役立ち、慢性腎炎の一部の症例も治療できます。実際には、アストラガルスよりもアトキの方が頻繁に消費されています。アストラガルスとアトキはどちらも薬用食品であることがわかっています。例えば、アンジェリカは女性の月経障害を治療することができます。 |
推薦する
ヤナギチャブの効能と機能
柳生姜は伝統的な漢方薬の一種です。古代中国の医学書にも柳生姜に関する記録があります。柳生姜は多くの病...
クコの実は水に浸けても大丈夫ですか?
ご存知のとおり、クコの実は咳や痰の緩和、美肌効果などがあり、私たちの生活に欠かせないものです。そのた...
ディアバイトグラスの効果と機能は何ですか?
鹿咬草はやや冷たい薬材で、腎臓を養い、脾臓と胃を調整するのに非常に効果的です。この薬材の主な機能は、...
男は見ると恥ずかしくなるが、食べると強くなる
乙女の実は錦灯籠とも呼ばれ、野生の果物ですが、一般家庭でも知られ、全国の山岳地帯や中山岳地帯で栽培さ...
ディクラノプテリス・ディコトマの効能と機能
ディクラノプテリス・ディコトマは、我が国で長い歴史を持つ、よく使われる伝統的な漢方薬です。今日はDi...
Dipsacus asperの薬効は何ですか?
Dipsacus asper は、別名「修道士の頭」とも呼ばれています。また、「魂還りの丸薬」とい...
アサルムオドラタムの効能と機能
あらゆる薬材の主成分を理解してこそ、その効能と機能をよりよく発揮することができます。ここでは、非常に...
タンポポとタンポポの違い
田舎ではタンポポのことはよく知られています。喉が痛いときや腫れているときは、タンポポを煮たり、水に浸...
カシア種子は1ポンドあたりいくらですか
レストランで食事を注文すると、通常、テーブルの上に大きな水の入ったポットが置かれ、店側が客に無料で提...
桑の葉はどんな病気を治すことができますか?
桑の葉は糖尿病の治療に効果があり、血糖値の上昇を抑制し、血糖値を下げるのに役立ちます。桑の葉を使って...
馬革の効能と機能
馬皮は、多くの人がよく知っているものです。馬皮が私たちにもたらす効能は、他の食品では得られません。で...
生高麗人参の効能と機能
日常生活において、高麗人参は多くの人々に非常に馴染み深いものです。高麗人参の薬効は非常に高く、滋養効...
段ボールの効能と機能
薬は生活の中でとても身近なものです。薬には多くの種類があり、薬によって病気の治療効果が異なります。薬...
イサティス根の薬効
イサティスの根は風邪に非常に良い治療薬です。イサティスの根をたくさん飲むと、インフルエンザウイルスの...
リーエベアポーの効能と機能
Li'e Bear Paw は、多くの人がよく知っているものです。Li'e Bear...