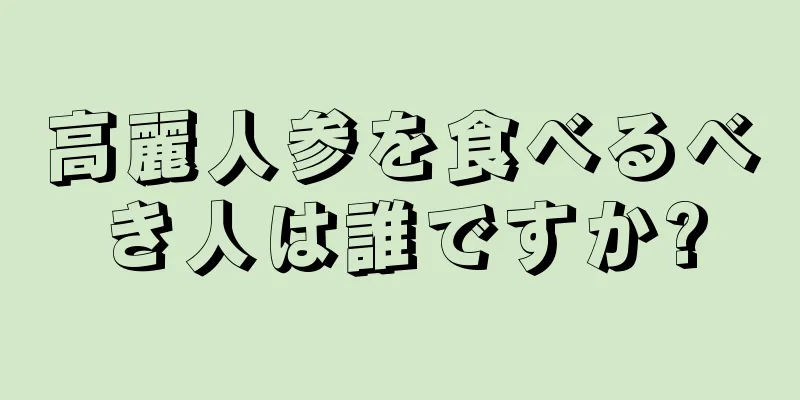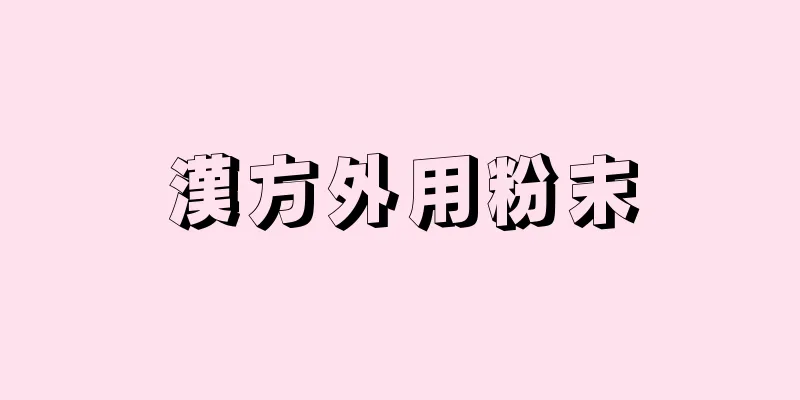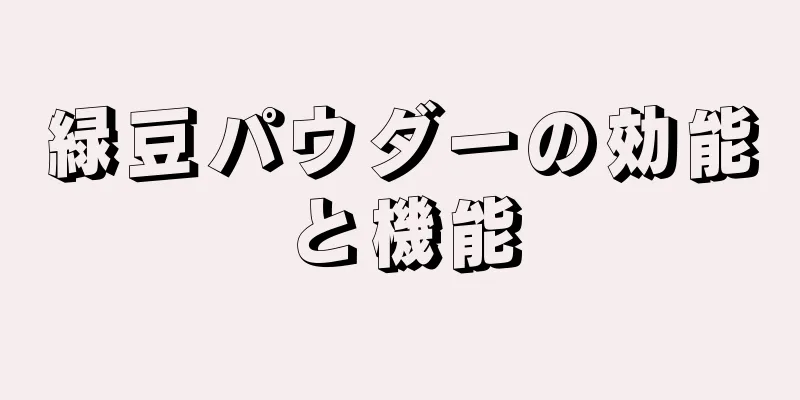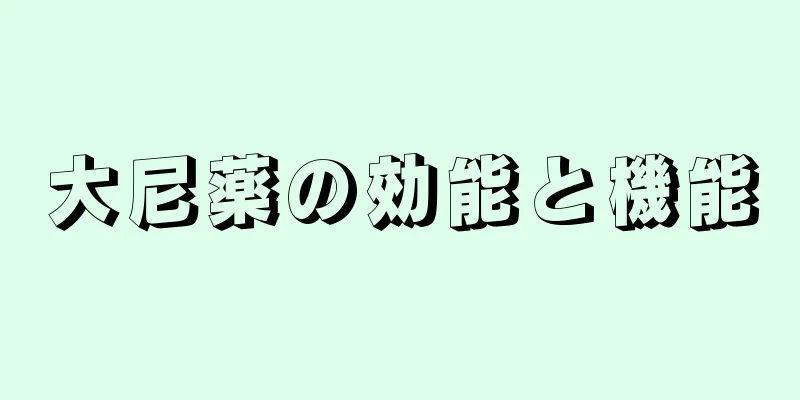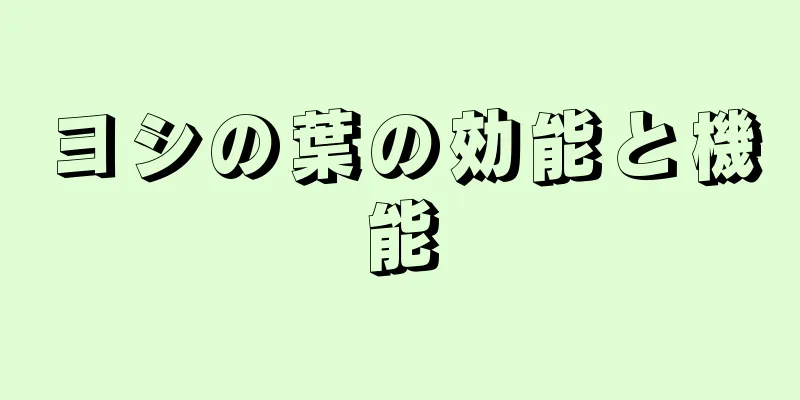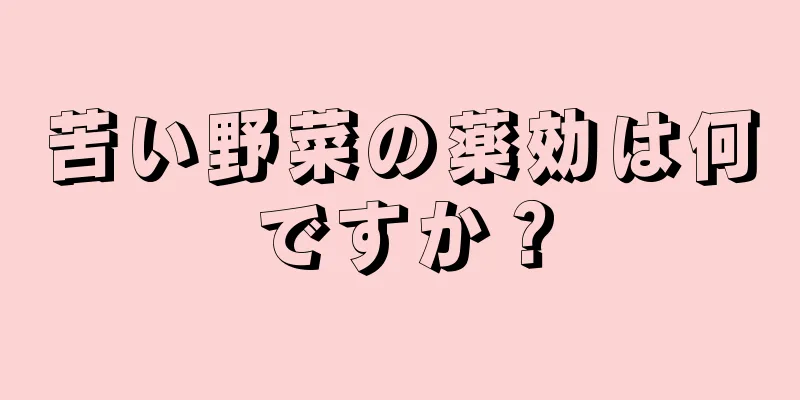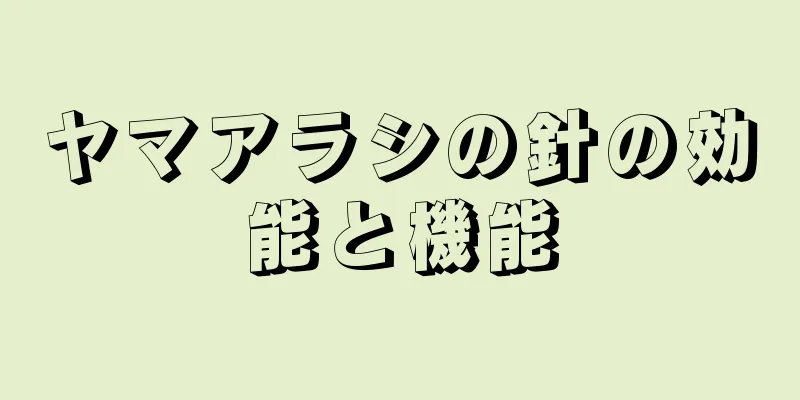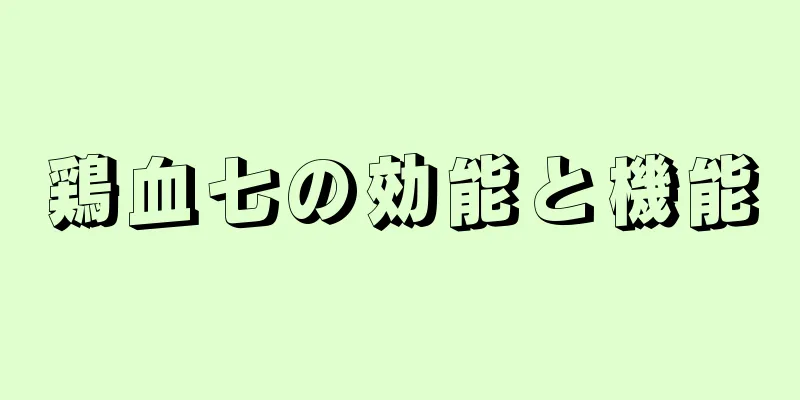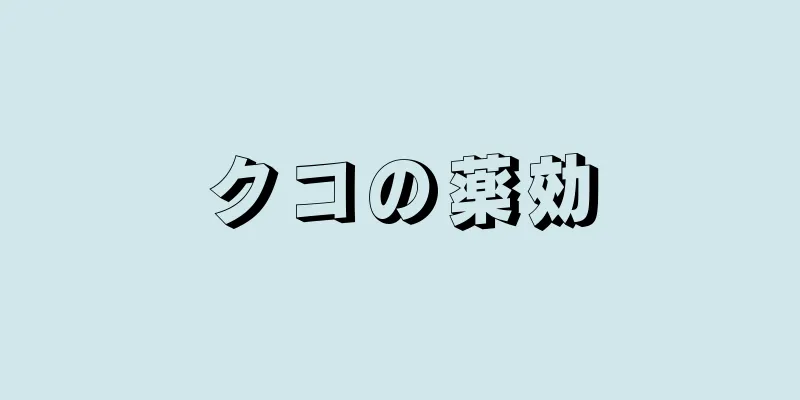一度に何粒の五味子を水に浸して飲めばいいですか?
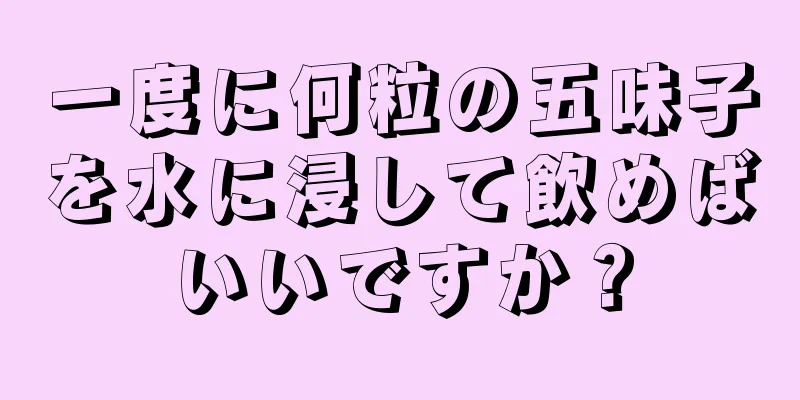
|
五味子は一般的な漢方薬です。五味子を摂取すると不眠症が緩和され、鎮静効果があります。健康に多くの利点があります。しかし、五味子には毒性があります。水に溶かした五味子を飲む場合は、医師に相談し、医師の指導の下で摂取するのが最善です。そうしないと、盲目的に五味子を水に溶かして飲んでも健康効果がないだけでなく、健康に害を及ぼす可能性があります。では、一度にどのくらいの五味子を水に浸すべきでしょうか? 一度に何粒のSchisandrae Chinensis種子を水に浸せばいいですか? 提案1 維子を水に浸すと、神経を落ち着かせる効果があり、クコの実と一緒に使うこともできます。 毎日、五味子を10グラム水に浸すだけで十分です。使いすぎる必要はありません。中医学では不眠症は肝臓、腎臓、心臓に関係していると言われているため、クコの実と一緒に使用することをお勧めします。 提案2 五味子とクコの実には、血液を養い、神経を落ち着かせ、肝臓を養う効果があります。一度に5〜10個の五味子とクコの実を水に浸し、1日1〜2回飲むとよいでしょう。 推奨事項3 五味子は腎臓を養い精気を高め、肺を養い体液を生成し、発汗を抑え下痢を止めます。 15グラム以上を水に浸さないでください。 勧告4 五味子を水に浸す場合は、10グラム程度を使い、熱湯に15分程度浸すのが最適です。 水に浸した五味子の飲み方 高麗人参と五味子茶 材料:高麗人参スライス4グラム、五味子50グラム、シソの茎6グラム、白砂糖100グラム。 作り方:高麗人参のスライス、五味子、シソの茎を鍋に入れ、適量の水を加えて30分ほど浸し、沸騰させて汁を抽出し、砂糖を加えて透明になるまで溶かします。 適応症: 気陰虚による慢性気管支炎、虚火昇、咳、喉の渇き、息切れ、疲労、言語障害のある方に適しています。 使用方法: いつでも、1日1回お飲みください。 五味子茶 レシピ:五味子3〜5グラム、緑茶0.5〜1.5グラム、蜂蜜25グラム。 使用方法: 五味子を弱火で少し焦げ目がつくまで炒め、沸騰したお湯に緑茶を入れて5分間煮出し、熱いうちに蜂蜜を加えてよく混ぜます。 1日1回、3回に分けて温かい状態でお召し上がりください。 効能: 精神を元気にし、腎臓と肝臓を養います。足腰の弱さ、耳鳴り、神経衰弱、慢性肝炎、肝虚によるめまい、視力低下などに効果があります。 杜仲茶 レシピ:トチュウ20グラムとシサンドラ・キネンシス9グラム。 使用方法:上記の薬を粗い粉末に挽き、魔法瓶に入れ、適量の沸騰したお湯を注いで浸し、蓋をして15〜20分間煮ます。こまめに飲んで1日以内に飲みきってください。 効能:肝臓と腎臓を養い、腎臓を養い、精を収斂し、腱と骨を強化します。 効能: 腎虚による腰痛、高血圧初期などのめまい、頭痛、めまい、不眠、腰や脚の衰弱、インポテンツ、精液漏、神経衰弱などの気力不足。 注意事項: 下半身の湿熱蓄積による精液漏および腰痛のある患者は、この製品を飲まないでください。 |
推薦する
トウモロコシの苞葉の効能と機能
トウモロコシの苞は、伝統的な中国医学で頻繁に使用される薬用物質であり、さまざまな病気の治療によく使用...
マザーワートには子宮を縮小させる効果がありますか?
マザーワートには子宮を収縮させる作用があり、取り返しのつかない結果を招く可能性があることをほとんどの...
松葉霊芝の効能と機能
霊芝は森の精霊としても知られ、古くから医師によって最高のものと考えられてきました。野生の松葉 Gan...
パルプ巻き籐の効能と機能
Glehnia littoralis は伝統的な漢方薬の一種です。特定の病気の治療において人体に非常...
エビ花葉の効能と機能
エビ花葉は栄養価が高く、薬効も高いです。以下では、漢方薬エビ花葉の効果と働きについて詳しくご紹介しま...
葉散花の効能と機能
私たちの生活において、フロスフロスの葉は、その非常に高い薬効価値から注目を集めています。それでは、葉...
水に浸したミカンの皮やクコの実を飲むと何の効果があるのでしょうか?
日常生活において、水に溶かした漢方薬を飲むことは、いくつかの病気を含む多くの実際的な問題を解決するの...
石米の効能と機能
石米は栄養価が高く、薬効も高いと言われています。以下では、中医学の石米の効果と働きについて詳しくご紹...
柴胡舒甘丸
薬は非常に一般的であり、異なる薬は病気の治療に異なる効果をもたらします。薬の使用も規制に従って行う必...
灰色のアザミの効能と機能
灰色アザミは生活の中で非常に一般的な薬用材料です。薬用食品や薬を作るのに使用できます。灰色アザミの用...
アメリカ人参の効能と機能
アメリカニンジンは、多くの高齢者が人生で好む健康食品です。伝統的な中国医学では、アメリカニンジンは非...
せむしソールの効能と機能
中医学では、病気の治療に漢方薬の使用が求められており、漢方薬の一種である羅果地もよく使われています。...
アヘンの効能と効果
多くの中国人にとって、伝統的な中国医学は長い歴史があり、副作用も少ないため、非常に信頼できるものです...
麻の腐敗の効能と機能
漢方薬としての麻布の薬効をご存知ですか?漢方薬は麻布をどのように病気の治療に利用しているのでしょうか...
Atractylodes macrocephalaの効果と機能は何ですか?
枸杞は我が国で最も一般的な漢方薬の一つで、長い薬用の歴史があり、『本草綱目』にも記載されています。そ...