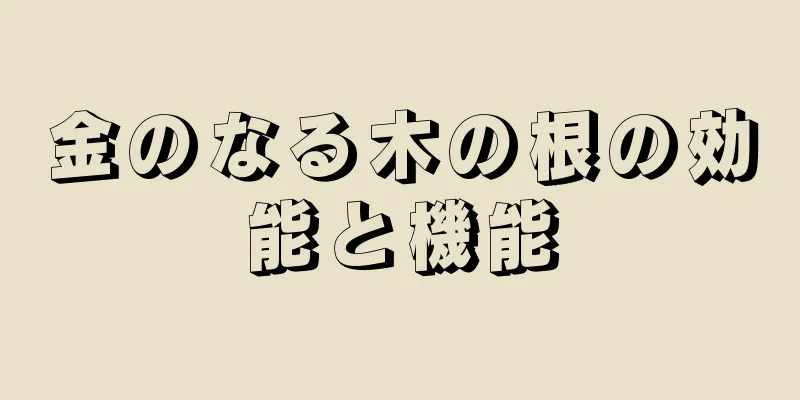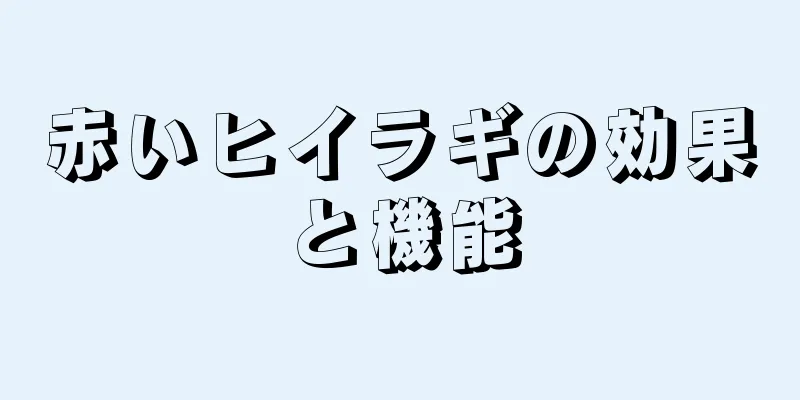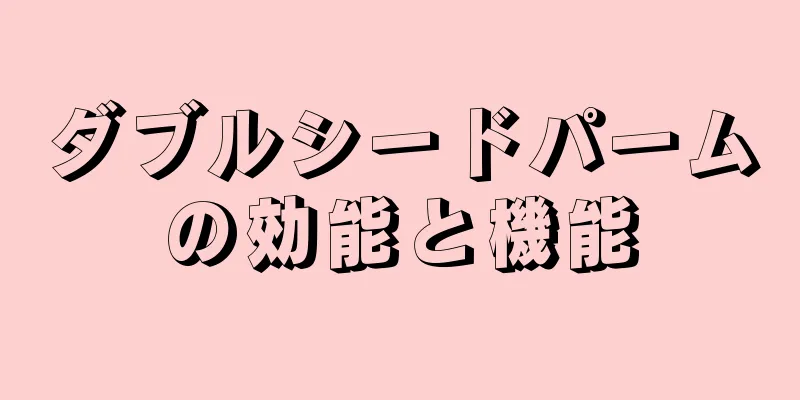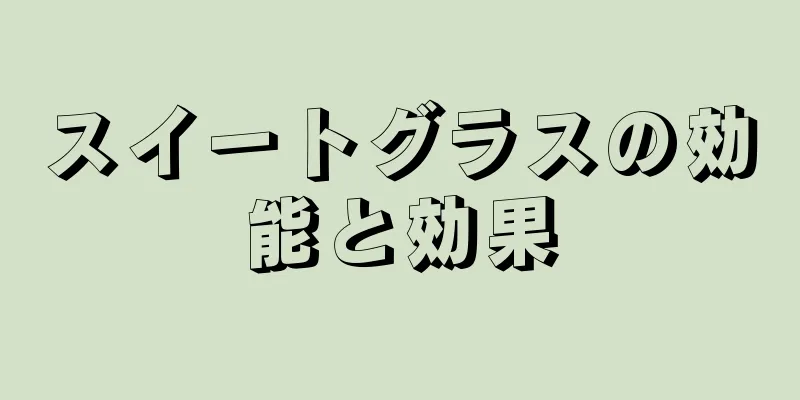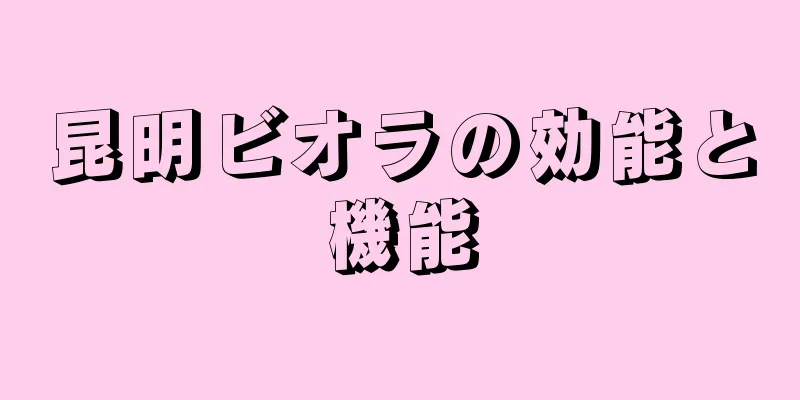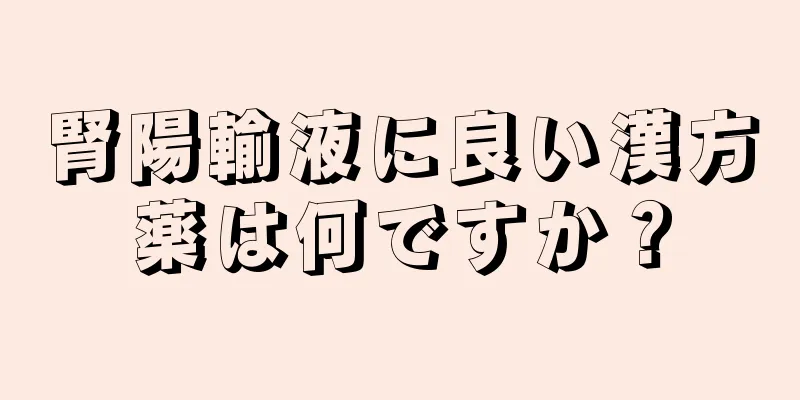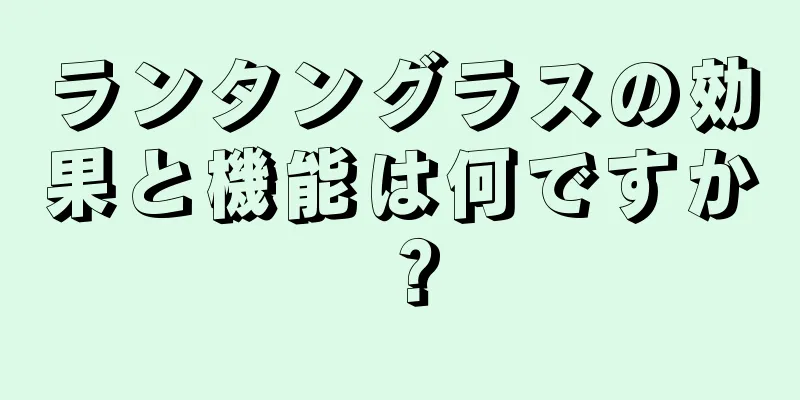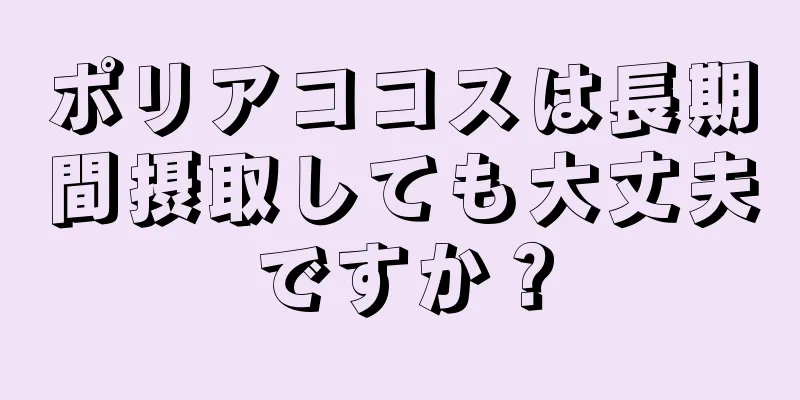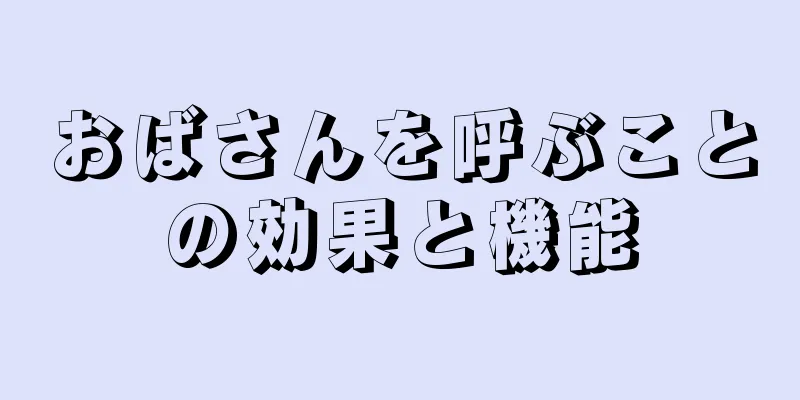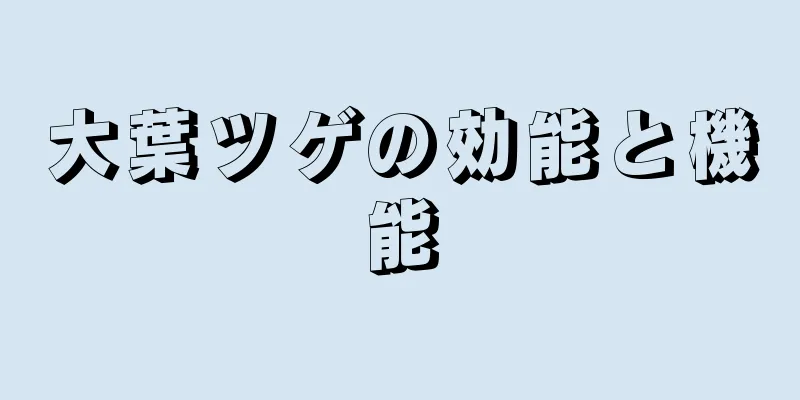バイモと一緒にビワを煮るとどんな効果がありますか?
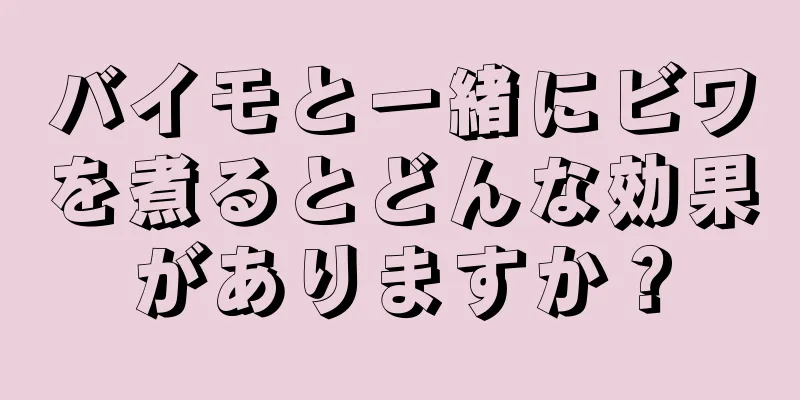
|
ご存知のとおり、ビワは美味しくて栄養価が高いだけでなく、健康価値も高いです。 『本草綱目』には、「ビワは五臓六腑を潤し、心肺を養う」と記されている。伝統的な中国医学では、ビワには痰を除去して咳を和らげ、水分の産生を促進して肺を潤し、熱を取り除いて胃を強化する効果があると考えられている。現代医学では、ビワにはビタミン、アミグダリン、リソルビトール、その他の抗がん物質が豊富に含まれていることも証明されています。では、ビワをバイモと一緒に煮込むとどんな効果があるのでしょうか?以下で詳しく見ていきましょう。 バイモとビワの煮物の効能 バイモ煮ビワの主成分はバイモで、清熱・解痰に効果抜群です。本品は主に乾熱咳嗽、寒咳嗽、風邪による咳嗽、老人の頻繁な咳嗽、咽頭痛および嗄声、胸苦しさ、肺虚弱による頻繁な咳嗽、体液乾燥、咽喉乾燥舌、黒痰、偽火上昇、喉頭炎による咽頭痛、気虚および痰過多、虚弱による乾咳、口臭および胃停滞、咽喉痒痒の治療に用いられます。糖尿病患者には適していません。 ビワとバイモの煮込みの作り方 1. ビワを洗い、芯と皮を取り除きます。 2. 氷砂糖、バイモ、ビワを用意します。 3.すべての材料をシチュー鍋に入れ、少量の沸騰したお湯を加えます。 4. シチュー鍋に蓋をして、鍋の中の水が沸騰したら食材を入れ、40分間煮込みます。 なお、甘いスープとして飲むだけの場合は、フリチラリア・シルホサを加える必要はありません。 2. お好みに応じて氷砂糖の量を調整してください。 3. このシロップは風邪の咳には適していません(舌苔が白くなり、夜間の咳は主に風邪の咳によるものです)。 以上がビワ入り川北煮の効能です。さて、ビワ入り川北煮について理解できましたか?同じような病気にかかっている方は、ビワ入り川北煮をお使いください。効果はやはり良好です。ただし、同じレシピが他の人には有効でも、必ずしもあなたに有効であるとは限りません。試してみる前に、この原則を理解していただければ幸いです。 |
<<: Fritillaria cirrhosaの用途は何ですか?
推薦する
高麗人参楊栄丸の効果と機能は何ですか?
人参楊栄丸は気血を補うことができます。人参の栄養価が含まれていることは周知の事実ですが、当帰、地黄、...
牛肺の効能と機能
伝統的な中国医学である牛肺は、その機能と効果により、実生活でよく使用されています。では、牛の肺にはど...
肝臓にダメージを与えずにツルドクダミを食べるにはどうすればいいですか?
多年草は非常に貴重な薬であり、食品の原料としても使用できますが、結局のところ、薬効成分を含む物質です...
血の出ない釘
中医学の観点から見ると、爪は体調を反映することもあります。特に、爪の半月の大きさは体の精気を表します...
Platycladus orientalis の葉で髪を洗うとどんな効果がありますか?
熱体質の人は白髪になりやすいことは誰もが知っています。実際、白髪は人に大きな影響を与えます。シデラキ...
幸運草の効能と機能
伝統的な漢方薬として、幸運草の薬効をご存知ですか?伝統的な漢方薬は幸運草をどのように病気の治療に使用...
サフランの保存方法
サフランの保存についてはどうでしょうか?誰もがそれが何なのか、何に使われるのか疑問に思っているに違い...
千金宝の効能と機能
千金宝は垂直に成長する伝統的な漢方薬です。葉だけでなく、根も薬として使用できます。葉は左右対称に成長...
川地龍の効能と機能
多くの中国人にとって、伝統的な中国医学は長い歴史があり、副作用も少ないため、非常に信頼できるものです...
自然分娩のデメリット
女性の場合、体調が許せば、必ず自然分娩を選択すると思います。体に手術をして消えない傷跡を残したい人は...
黒クコの実は沸騰したお湯に浸した方が良いですか、それともぬるま湯に浸した方が良いですか?
黒クコの実は実生活で非常に一般的な栄養食品です。多くの栄養素とビタミンが豊富に含まれており、体に栄養...
ネギの効能と機能
ネギって何だかご存知ですか?ご存知の方は、ネギの効果や働きを理解していますか?伝統的な薬用素材である...
気血を補う漢方薬は何ですか?
現代社会において女性の地位がますます高まるにつれ、女性の健康に焦点を当てた話題が増えています。女性は...
多裂葉タンポポの効果は何ですか?
タンポポは誰もがよく知っています。タンポポは強靭な生命力を持つ野生植物として、人々に高く評価され、特...
仙草の効果と機能とは
不老不死の薬草といえば、文字通り、人を不老不死にし、いつまでも若々しい外見を保つことができるという意...