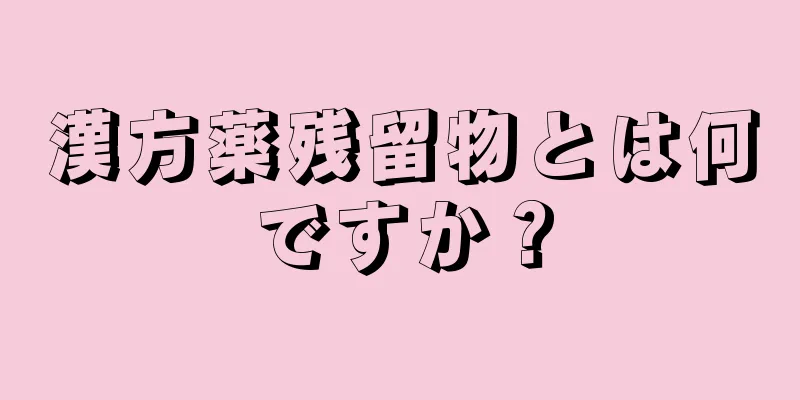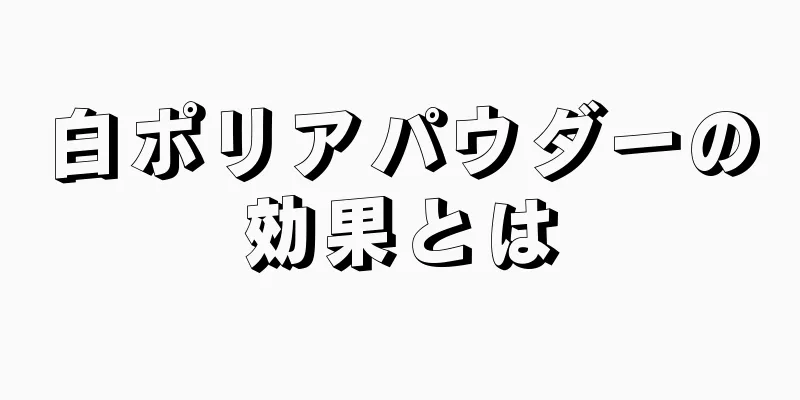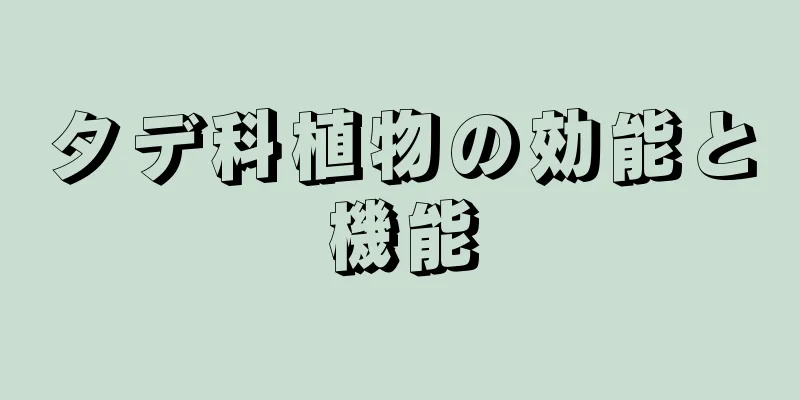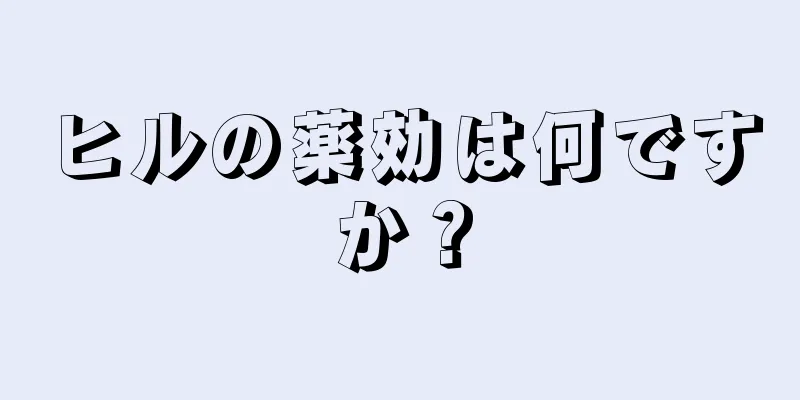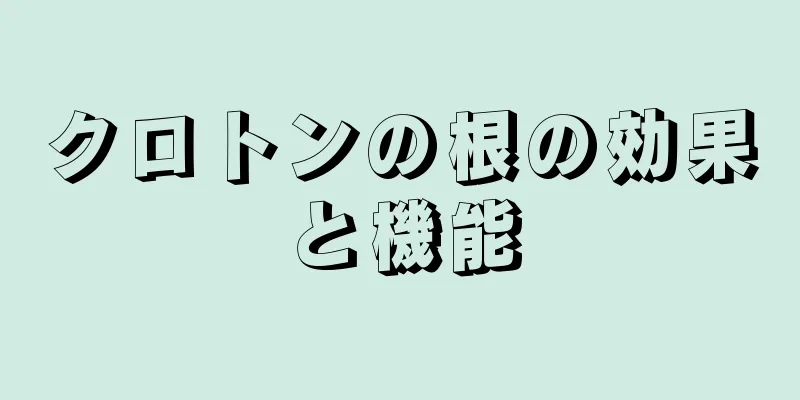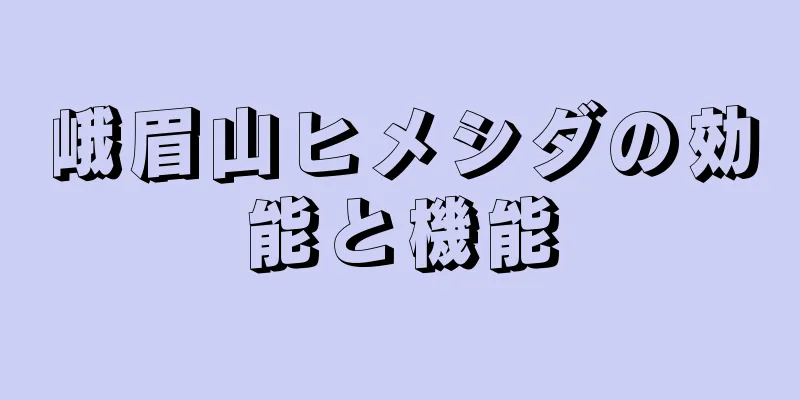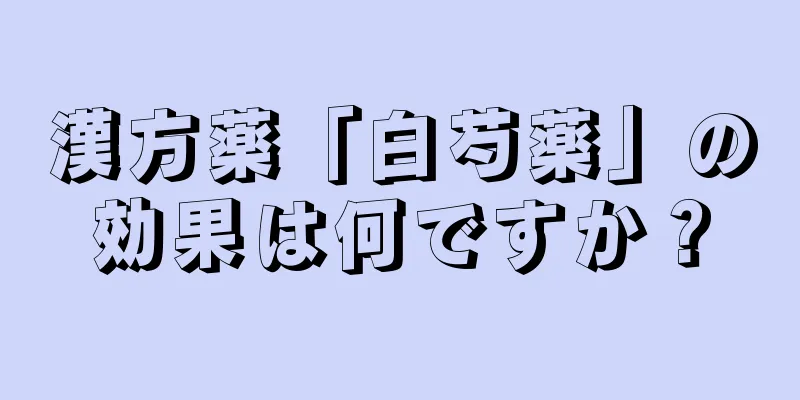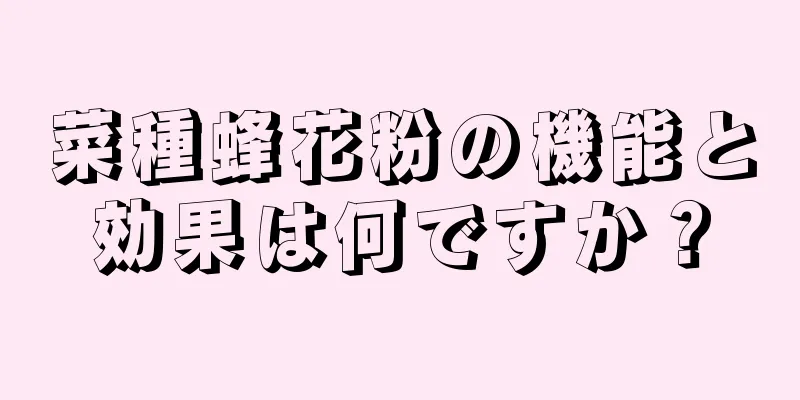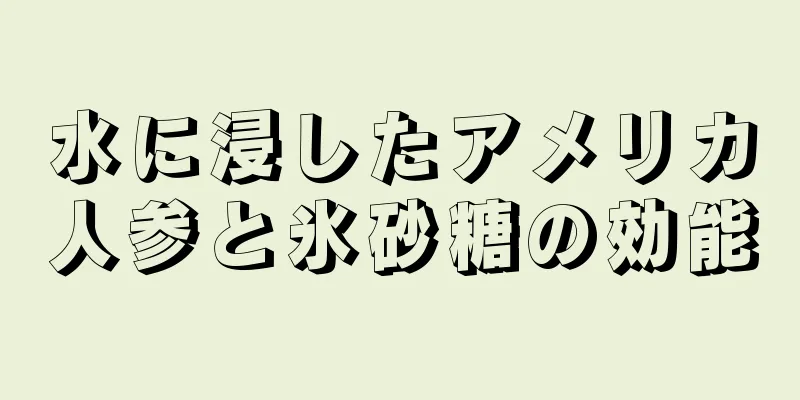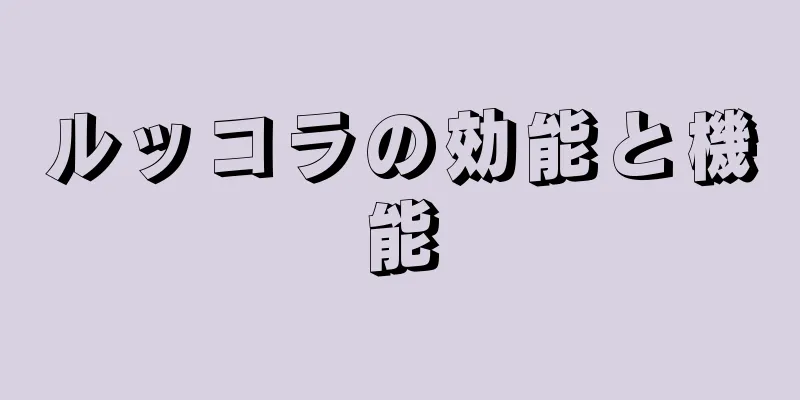クコの実の過剰摂取による副作用
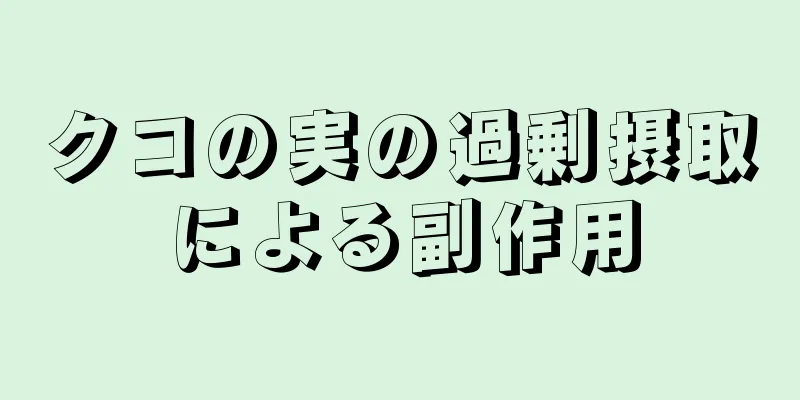
|
クコの実について話すとき、人々は一般的にそれが人間の健康に良い食べ物であることを知っており、その効能について考えます。確かに、クコの実には多くの機能があり、腎臓を養うのにも良い役割を果たします。しかし、完璧なものはありません。クコの実にも欠点があります。正しく食べなかったり、タブーに触れたりすると、副作用が発生します。では、クコの実を食べすぎるとどのような副作用があるのでしょうか。 クコの副作用:クコはすべての人に適しているわけではない 夏季や陰虚の人はクコの実の摂取量を減らす必要があります。クコの実は甘くてマイルドですが、過剰摂取は腹痛を引き起こす可能性があるため、特に生で食べる場合は摂取量を減らす必要があります。 クコの実は栄養価が高く、治療効果も高いのですが、すべての人に適しているわけではありません。体を温める作用が非常に強いため、風邪や発熱、炎症、下痢などの症状がある人は食べないようにしましょう。 クコの副作用2:過剰摂取 どれだけ良いものでも、過剰に摂取すると副作用が出ます。子どもの頃、食べ過ぎで鼻血が出ました。 クコは体質が弱く抵抗力が弱い人に適しています。しかし、摂取過程においては、長期間継続し、毎日少しずつ食べなければ効果は現れません。クコの実には、ベタイン、アミノ酸、カロチン、ビタミンB1、B2、C、カルシウム、リン、鉄などの成分が含まれています。定期的に摂取しても副作用はありませんので、安心して摂取できますが、欲張って一気に太った男を食べたいと思わないでください。それは急がば回れになるだけです。以下の点に留意する必要があります。薬は、その性質、つまり薬効成分を利用して病気を治療します。補陰薬は虚証にも用いられるため、健康で虚証のない人は使用すべきではありません。また、邪気が強くても義気が弱くない人は、敵を家に留めておくことを防ぐために、補陰薬をむやみに使用すべきではありません。 クコの副作用3:目の不快感を引き起こす クコの実を過剰に摂取すると、目が赤くなったり腫れたり、不快感を覚えたり、視界がぼやけたりするなどの副作用が起こる人もいます。健康的な食事の観点から、そのような人はクコの実を食べてはいけません。 クコの副作用4:温熱効果が強すぎる 体を温める作用が非常に強いため、高血圧の方、過敏な性格の方、肉類を多く摂取して顔が赤い方、風邪や発熱、炎症、下痢などの症状がある方は食べないようにしましょう。 上記は過剰摂取による副作用です。強壮剤の過剰摂取は厳禁です。クコの実も例外ではありません。一般的に、健康な成人は1日あたり約20グラムのクコの実を食べるのが適切ですが、治療効果を得たい場合は1日あたり約30グラムを食べるのが最適です。現在、クコの実の毒性に関する多くの動物実験により、クコの実は非常に安全な食品であり、毒素を含まず、長期間にわたって摂取できることが証明されています。 |
>>: クコの実を水に浸して腎臓に栄養を与えることはできますか?
推薦する
ヒイラギの葉の効果と働き[写真]
柊の葉[写真]は、長い歴史を持つ中国の伝統的な薬材として有名です。今日はヒイラギの葉について学びます...
ツルドクダミの効果
漢方薬は、現在では大変一般的です。漢方薬には多くの種類があります。漢方薬を選ぶときは、医師のアドバイ...
桜の枝の効能と機能
桜の枝は伝統的な漢方薬の一種で、古代には病気の治療に桜の枝を使った例もあるので、安心して食べることが...
エリスリナの葉
エリスリナ葉についてご存知でしょうか、またその効果や働きについてご存知でしょうか。エリスリナ葉の価値...
すとうの効能と機能
蘇豆は非常に栄養価が高く、貴重な薬用物質です。蘇豆を定期的に食べると、非常に良い効果と機能が得られま...
ショウズキの根は痛風に効きますか?
寿树根は一定の栄養価と多くの機能を備えた食品です。例えば、陰虚、咳、喉の乾燥などの症状を緩和すること...
ドライオプテリスビカラーの効能と機能
社会の発展と国際交流の緊密化に伴い、医学を学ぶ人の大半は西洋医学の影響を強く受け、漢方医学を学ぶ人は...
水に浸したミカンの皮を飲むことの効能
みかんの皮は、非常に一般的な漢方薬です。病気の治療に多くの用途があります。したがって、治療できる病気...
清天奎の効果と機能は何ですか?
青田奎はラン科クワズイモ属の植物で、単葉蓮、珠葉とも呼ばれ、薬効が高く、主に清肺、咳止め、脾臓の強化...
岩セダムの効能と機能
セダムは非常に一般的な中国の薬用材料です。非常に一般的ですが、多くの魔法の効果があります。以下で見て...
4種類の漢方薬が女性の健康に良い!
伝統的な中国医学では、冬に温滋養強壮漢方薬を使用すると人体の内臓の活力を高めることができ、この季節の...
犬の爪樟脳の効能と機能
クスノキは、我が国において長い歴史を持つ、伝統的かつ一般的に使用されている有名な漢方薬です。今日はC...
シナモンの機能と効果は何ですか?
シナモンの効果をご存知ですか?実際、痰を除去し、咳を和らげるのに役立つだけでなく、放射線と闘い、男性...
タツノオトシゴを使った煮込み料理
福美来を使った最高のスープは何ですか?福美来は、陽を強化し、腎臓を養う効果がある漢方薬です。健康を養...
バイデンピローサは血圧を下げることができますか?
多くの人が外へ遊びに行くのは、自然と触れ合い、自然の息吹を感じ、心身を整えることができるからです。し...